第2章 産業廃棄物処理の構造と機能
1 産業廃棄物処理の構造
(1) 産業廃棄物の処理行程
全ての廃棄物は,図 6に示す経路に沿って処理される。このことは,産業廃棄物と一般廃棄物に共通することであり,例外はあり得ない。産業廃棄物処理業者は,図 6に示す行程のうちの収集から最終処分までの部分の多くを担っている。もし,この経路から外れる処理があるとすれば,それは不法投棄である。
図6 廃棄物の処理行程
全ての廃棄物処理行程の最終的な行く先は,最終処分場すなわち埋立である。リサイクルとは,廃棄物の中から資源を選び出すことであり,どのようなリサイクルをしても埋め立てなければならない残渣は必ず発生する。製造業の事業者などがゼロエミッションを達成したことを喧伝することがあるが,そこで言っているゼロエミッションとは,その事業者が発生した廃棄物を100%リサイクル施設に持ち込むことである。工場から搬出された資源化物は,リサイクル施設の段階で産業廃棄物を発生する。すなわち,産業廃棄物の発生段階を製造工場から,リサイクル施設にシフトしたに過ぎない。このことを模式的に示したのが図 7である。
図 7 ゼロエミッションの概念
図 8に産業廃棄物処理の取引の流れを示した。産業廃棄物処理に関わっている主体は,(1)事業者,(2)収集運搬業者,そして(3)処分業者である。収集運搬と処分を1つの産業廃棄物処理業者が一括して行うこともある。法律が産業廃棄物取引における仲立ち行為を嫌っているために,産業廃棄物処理取引において商社等の関与は公式的にはあり得ない。法律の建前では,事業者は,収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約を結ぶよう求められている(注[1])。すなわち,廃棄物の実体の流れは,(1)事業者→(2)収集運搬業者→(3)処分業者であるけれど,契約については,(a)事業者vs. 収集運搬業者の契約があり,それとは別に更に(b)事業者vs. 処分業者の契約を結ぶことになる。すなわち,収集運搬業者と処分業者の間には取引関係が存在せず,一見すると収集運搬業者は流通業者の機能を果たしているようであるが,法律の規定ゆえにそうした機能は持ち得ない。
図 8 産業廃棄物処理取引の流れ
ただし,法律は処理料金の流れを規定していない。契約どおり,収集運搬業者への支払いと処分業者へのそれを分離して実施することがあるが,収集運搬料および処分料を含むトータル額が事業者から収集運搬業者へ一括して支払われた後に,処分業者への支払いは収集運搬業者からなされる等のケースもあり,状況を複雑にしている。しかしながら,法律が規定している産業廃棄物処理委託契約は,不法投棄・不適正処理がなされた場合の,事業者と産業廃棄物処理御者の責任関係を明確にすることを目的としているのであり,商業上の必要な事項は,契約の当事者が別に決めなくてはならないのである。実際のところは,法律が規定する事項を中心とする契約書を用いるという業界慣行が確立しており,カネの流れを契約書で定めている例は少数である。
(2) 産業財の中での位置づけ
産業廃棄物処理サービスは,生産財として取引される。商品の分析については,Kotler(2003)が様々な視点からの有用なアプローチを提案している(注[2])。ここでは,それらを用いて,産業廃棄物処理サービスを位置づけてみる。
Kotlerは,まず産業財を(1)原材料・部品,(2)建物・工場設備,そして(3)補給品・ビジネスサービス,の3つに分類している。特に補給品については,維持(maintenance)・補修(repair)・運用(operating)に係るものとして,MRO goodsと括っている。この分類に従えば,産業廃棄物処理サービスは,補給品・ビジネスサービスに分類されることになる。補給品・ビジネスサービスは,中小のサプライヤーが請け負うことが多く,その選択はサプライヤーの評判やスタッフを評価して行われるとしている。
一方,消費財の分類として,(1)日用品,(2)買い回り品,(3)非探索品(unsought goods)を示している。消費財で言うところの非探索品とは,火災報知器・墓石・保険のように,買い手は普通それらのことを知らないし,それらを買うことを考えもしないものである。それらのセールスには,広告やセールスマンの活動を必要とするという。産業財に敢えてこの分類を適用すれば,産業廃棄物処理サービスは,事業上の売上に直接貢献しない非探索品に該当する。
さらに,商品の位置づけを分析するツールとして,5段階の製品レベルを提示している。ここで言う「製品」を「サービス」に置き換えてモデルとすれば,産業廃棄物処理は,次のように分析されるだろう。
- コア便益:廃棄物が目の前から無くなること
- 基本サービス:産業廃棄物収集サービス
- 期待サービス:きれいで,迅速,かつ適法な産業廃棄物処理サービス
- 拡張サービス:収集から処分までの追跡可能性など
- 潜在サービス:環境関連の情報提供サービスなど
産業廃棄物処理サービスは,基本的な部分で他社との差別化を実現することが難しいため,図 9に示す外縁部分(拡張サービス~潜在サービス)での競争が想定されるが,現実のところは,そこでの目立った提案がなされていないし,買い手の側がそれらを評価することは少ない。なお,図 9は,Kotlerのオリジナルは物財の特性を説明するものであって,コア便益を基礎製品~潜在製品が取り囲むようになっているが,産業廃棄物処理はサービス財であるので,コア便益を基礎サービス~潜在サービスが取り囲むように修正して,産業廃棄物処理サービスの分析の用に供した。
図 9 5段階製品モデル(Kotler, 2003から修正)(注[3])
(3) サービス取引としての位置づけ
上原(1999)は,マーケティングの展開は流通構造のあり方に依存することを述べている(注[4])。産業廃棄物処理についても例外でなく,そのマーケティングは流通構造に依存するといえるだろう。しかしながら,産業廃棄物処理の流通構造は一般の物財のそれと比較して特異な点もある。廃棄物は,マイナスの価値を伴う物体であり,通常の物財,グッズ(goods)と対比してバッズ(bads)と呼ぶ(注[5])。産業廃棄物処理の流通の特異性は、それがバッズであることに起因する部分も多い。
産業廃棄物処理の取引では,カネの流れとモノの流れの関係が,一般の物財取引のそれとは逆である。すなわち,一般の物財取引では,財貨と代金は交換関係にあり,その流れは互いに対向する。しかし,産業廃棄物処理においては,実体である産業廃棄物と代金の流れは,一般の財貨のそれとは違って並行の関係にある(図 10)。
図 10 モノの流れとカネの流れの関係
また,産業廃棄物処理における在庫と資金の関係も,一般の財貨におけるそれとは逆の関係になる。一般の物財取引においては,在庫を多く持てば持つほど商人の手許の資金は減る。しかし,廃棄物処理取引においては,未処理のまま保管されている廃棄物の量が増えれば増えるほど廃棄物処理業者の手許の資金は増える(図 11)。これは,事業者にとって産業廃棄物処理サービスのコア便益とは,産業廃棄物が目の前からなくなることであって,最後まで適正に処分されることではないため,処理代金は産業廃棄物が引取られた段階で支払われるためである。
図 11 在庫と資金の関係
このように,産業廃棄物の取引は,一般の物財のそれとは逆の構造を有することがわかるが,産業廃棄物処理の取引はサービス取引であるので,カネの流れ・モノの流れと並んでサービスの流れを考える必要がある。この観点に立てば,産業廃棄物処理は,貨物輸送や自動車修理,理美容などのサービス業と変わるところはない。すなわち,産業廃棄物処理の特殊性とは,それがマイナスの価値をもつ商品,バッズ (bads) を扱うことであり,不法投棄・不適正処理の原因もバッズ取引であることに帰するべきなのである(図 12)。
図 12 モノ・カネ・サービスの流れ
流通経路分析の方法としては,Bucklin (1966) が体系立てた枠組みを提案している(注[6])。そこでは,流通経路をいくつかの経路過程に分割し,ロットサイズ,延期・投機の概念を含むデリバリー時間,市場の分散度などのパラメーターを操作して,種々の分析を行う方法を示すとともに,実際例を対象に分析を行っている。しかし,産業廃棄物処理取引の分析にこの枠組みを適用することは困難である。なぜならば,法律が産業廃棄物処理取引における仲立ち行為を嫌っているために,財貨の所有権の移転から利益を得る商人が公式的に存在せず,廃棄物の実体のハンドリングを伴う取引だけが存在する流通構造になっている。このことを詳しく説明すれば,まず廃棄物処理法は,事業者が産業廃棄物の運搬と処分を委託する場合に,運搬業者と処分業者のそれぞれと直接契約を結ぶことを求めている(注[7]);また,産業廃棄物処理業者が,受託した産業廃棄物を他の産業廃棄物処理業者に再委託することを原則禁止している(注[8]);これらの規定のために,商社等が産業廃棄物処理の契約に加わることが困難になっているという構図になっているのである。
また,産業廃棄物処理取引においては,物流の途中で在庫を持つことが厳しく制限されている。たとえば,産業廃棄物の収集運搬過程での保管は,積替えに伴うものに限ることとし,その場合の保管量を1日あたり搬出量の7割に制限している(注[9])ほか,中間処理施設での産業廃棄物保管量にも厳しい制限が課せられている。そのため,流通論で言うところの投機の概念を適用すべきケースは殆どない。そして,マイナスの経済的価値を持つバッズ取引であることが,産業廃棄物処理取引のBucklinの分析枠組みへの適用を困難にする最大の要因である。
産業廃棄物処理サービスの中で,埋立の位置づけは特徴的である。埋立は,産業廃棄物を処分する空間を提供するとともに,受け入れた産業廃棄物を長期にわたって保管・管理するものである。埋立に使用する空間は,再生不可能な資源であるが,その確保には,時間その他の投資と幸運が必要である。すなわち,埋立処分場の開設までには,計画開始から5年~10年程度の時間を要することは希ではなく,また計画を進めても結局は処分場の開設を断念することになり,莫大な投資が無駄になるケースも多い。埋立を確保するということは,産業廃棄物処理業者にとっては仕入れにあたるが,一度に10年分くらいの仕入れをすることになり,大きな投機である。しかし,この仕入れに関しては,量的および時間的な調整は事実上不可能である。すなわち,埋立を設置しようとする産業廃棄物処理業者は,非常に大きな不確実性に対して投資をしなければならないのである。
2 産業廃棄物処理の機能
(1) 価値の創出に着目した分析
マーケティング研究では,人間と人間の関係性の構築が論じられている。マーケティングは商品を売ることを目的とするが,その目的に沿って,人間と人間の関係の構築メカニズムについての研究が深められている。経済学的視点では,市場取引を中心とする視座から系全体の動きを分析対象とする一方,マーケティング視点では,売り手と買い手が関係を構築し,あるいは意思決定をする過程を分析対象とするので,両者は互いに補い合う。廃棄物をはじめとする環境問題には,ステイクホルダー間の関係性の要素が大きい。それ故,ここにマーケティング視点を応用することができるはずである。
産業廃棄物処理取引を理解するにあたり,物財の所有権移転ではなく,効用の創出にフォーカスした概念枠に注目したい。商取引を売り手と買い手の間の関係構築であると捉えるならば,物体を介した価値の交換と考える必要はない。大友(2001)は,買い手が欲しているのは,効用であることを強調している(注[10])。大友は,マーケティング・コミュニケーションの目的を論じる中で,財貨の意味的効用の重要性に着目している。すなわち,まず,売り手が展開するマーケティング活動の目的は,その財貨を市場の買い手に認めて貰うことと,その財貨を購入してもらった者に効用をもたらすことであるとしている。そして,効用とは,買い手の欲望を充足する,あるいは問題を解決するという財貨の持つ特性であるとした上で,財貨が提供する物理的効用がそれを所有・消費する者が実感する意味的効用とは必ずしも一致しないことを論じている。つまり,財貨の価値は物体の価値ではなく,それを所有・消費することによって得られる意味的効用こそが真の価値だということになる。大友の主張は,物財の価値を介さないサービス財取引や,マイナス価値の物財であるバッズ取引に適用した場合,事象を単純化して説明することができる。
買い手が物財を欲している場合でも,買い手が真に欲しているのはその物財がもたらす効用である。逆から見れば,売り手が供給しているのも,物体としての商品ではなく,効用である。大友の概念に類似したものとしては,Vargo and Lusch (2004)が提唱しているService Dominant Logic(S-Dロジック)がある(注[11])。S-Dロジックにおいては,物財の取引であってもサービスが提供されているとする。すなわち,物財がもたらす効用をサービスと表現しているのである。また,売り手と買い手は,価値と貨幣を交換するという関係でなく,ともに生産者(creatorおよびco-creator)として協力し合って価値(サービス)を創出するという。また,生産者らが価値創出のために操作する対象をオペランド資源(operand resources),オペランド資源を操作するために用いる資源をオペラント資源(operant resources)と定義するが,当然それは物質的・非物質的による類型化ではない。後述するAlderson (1964) の交変系概念は,物財の流通をもとに構築されたものであるが,大友やVargoらなどの効用を価値の本体と位置づけて,価値の創出に着目する概念を当てはめることで,サービス財取引やバッズ取引についても,Aldersonの交変系概念を適用して理解することが容易になる。
流通の概念枠は,物財の交換を捨象することで,環境問題への適用を容易にする。環境経済学の概念では,バッズ取引をマイナス価値の物流として理解することは,上に述べた。取引から物体を捨象して,価値の移転もしくは効用の創出と理解すれば,サービス財取引もバッズ取引も通常の物財(グッズ)取引と同じ分析枠組みを適用して理解することが出来る。なお,前節では,Kotlerの5段階製品モデル(図 9)に産業廃棄物処理サービスを当てはめるのに,「製品レベル」を「サービスレベル」と置き換えて分析したが,効用(価値)の創出に着目する概念を適用するならば,このような置き換えは不要である。
ここでは,S-Dロジックを適用して,廃棄物処理サービスが創出する価値を検討することとする。S-Dロジックでは取引の概念を単純化し,売り手と買い手を生産者として括っている。そして,価値と貨幣の交換という概念さえ単純化して,両生産者によるサービス(効用)の創出とする。このS-Dロジックの枠組みを適用して,廃棄物処理サービスの構造と機能を分析した結果が図 13である。行為の主体たる生産者は,事業者と産業廃棄物処理業者である。操作の対象,オペランド資源は廃棄物であるが,その処理のために動員される資金・技術・機材・労働などの資源は,オペラント資源に該当する。オペラント資源のうち、無形であり形式化が困難なものとしては、産業廃棄物処理業者が提供する技術・実績・業者間ネットワーク・処理施設地元の理解などがあり、事業者はそれらに対して、遵法意識・公衆衛生への欲求・環境に関する規範意識などを以て応じるが、これらもまたオペラント資源である。これら技能や知識(skill and knowledge)として括られるオペラント資源は、産業廃棄物処理業者と事業者の交渉を経て変化し得る。たとえば、事業者が高度な処理技術を要求すれば、産業廃棄物処理業者は要求に応えるべく自らの技術を高度化するだろう。逆に、産業廃棄物処理業者がもたらす情報によって、事業者の意識が変化することもある。また、相手が持つオペラント資源は、産業廃棄物処理業者と事業者の双方にとって、取引相手を選択する基準となる。一方,廃棄物処理サービスから創出される価値は,美的価値の回復・空間の創出・法的責任からの解放・環境汚染の防止・公衆衛生の向上・資源の回復・利潤などである。
図 13 産業廃棄物処理サービスの効用創出の構造
(2) 価値の分配
産業廃棄物処理が価値を創出する仕組みをS-Dロジックで分析することで,産業廃棄物処理サービスの特異性は,創出される価値の分配の複雑性にあることが見えてくる。あらゆる商取引で,売り手と買い手にとっての関心事は,創出される効用(価値)の自己への分配の大きさと,それを得るために投入する資源の必要量である。これらを調整するために,売り手と買い手は互いに交渉を行い,また取引相手を選択する。通常のグッズ取引では,プレイヤーは①売り手と②買い手だけであり,①も②も自己の利益の最大化だけを考えて,自由に相手を選択できる。ところが,産業廃棄物処理サービスでは,効用を創出する主体は,①産業廃棄物処理業者と②事業者であるが,産出した価値の分配を受けるのは,①と②に加えて,③生活環境を共有する地域住民や公共セクターであり,分配の決定にはこれら3者が関与することになる。このことが,グッズ取引とバッズ取引の最大の相違点である。①と②は,③について選択の自由はない。産業廃棄物処理が創出する効用の分配にあずかる①~③の各ステイクホルダーの価値基準は一致しない。①産業廃棄物処理業者は,利潤をなるべく大きくしたい;②事業者は費用を最小化したい;③地域住民や公共セクターは,環境汚染防止や公衆衛生分野への分配を大きくしたい。こうした条件下で,各ステイクホルダーの要求の調整に失敗したケースこそ,不法投棄・不適正処理・種々の係争であると解釈できよう。これらのことを一般のグッズ取引と比較して図 14に整理した。
この図をもとに,実際のグッズ取引とバッズ取引をあてはめてみよう。図 14の上(グッズ取引)には,物財の取引ばかりでなくサービス財の取引についても適用可能である。例えば,サラリーマンが仕事の帰りに居酒屋に寄って,軽く酒を呑み肴を食べる場面に当てはめてみる。ここで,買い手はサラリーマンであり,売り手は居酒屋の親爺(店主)である。図中に示しているマーケティング行為とは,仕事に疲れたサラリーマンに席と酒と肴を提供することである。このマーケティング行為のために,居酒屋の親爺とサラリーマンはそれぞれ投資を行う。居酒屋の側の投資は,酒を呑ませるための場所・酒・肴・親爺の労働などであるが,サラリーマンの側の投資は居酒屋に支払う飲食代金である。一方,operand資源は,一日の仕事に疲れたサラリーマンの肉体と神経である。そして,マーケティング行為を通じて創出される価値は,空腹の緩和・肉体的活力の回復・精神的な癒しなどと,利潤である。これらは,買い手と売り手の間で配分される。
図 14の下のバッズ取引では,グッズ取引を構成する要素に加えて,地元住民・公共セクターが配置される。産業廃棄物処理の取引において,地元住民・公共セクターは,一般に取引の当事者と意識されることはないが,実は価値を創出するために投資を行っているのであり,取引主体として位置づけられるべき存在である。ここで言う地元住民・公共セクターによる投資とは,廃棄物処理施設の立地を受け入れ,地域への廃棄物の搬入を認めることであり,「受苦」と表現されることもある。廃棄物処理によって創出される価値は,図 13に示すとおりであるが,これらは投資を行った3者に分配される。ここで特に注目すべきことは,創出される価値のうち,美的価値向上や環境汚染防止などは,もっぱら地元住民・公共セクターに分配されるべきものであることである。つまり,産業廃棄物処理業者にとっての顧客は,まず廃棄物を発生する事業者であるが,実はそればかりでなく,廃棄物処理施設が立地する地元住民・公共セクターもまた顧客なのである。産業廃棄物処理においては,地元住民・公共セクターは,意図しなくても廃棄物処理行為に投資をして価値創出に関与しているのである。それゆえ,地元住民・公共セクターは,創出された価値の分配を受ける権利があるのである。
価値と貨幣の交換に着目する経済学の分野では,廃棄物はマイナス価値のbadsであり,売り手と買い手の間で処理できず系外に放り出される廃棄物を外部不経済と呼ぶが,価値の創出に着目するマーケティング視点を適用すれば,廃棄物処理は価値を産み出す行為であり,地元住民・公共セクターは価値創出に参画する存在,S-Dロジックの概念枠を借りれば共同生産者である。したがって,地元住民・公共セクターは,廃棄物処理を規制し廃棄物処理の障害となるものと位置づけられるものではないのである。
前節では,産業廃棄物処理を図 9のKotlerの5段階製品モデルにあてはめたが,それは産業廃棄物処理サービスの直接の買い手である事業者の視点によるものである。地域住民や公共セクターにとっての産業廃棄物処理を5段階モデルにあてはめれば,次のように分析されるだろう。
- コア便益:生活環境を悪化しないこと
- 基本サービス:法律の規定に従った産業廃棄物処理
- 期待サービス:生活環境の保全に配慮した産業廃棄物処理
- 拡張サービス:雇用など地域経済への貢献や,地域コミュニティとの交流・融和
- 潜在サービス:産業廃棄物処理業者の文化活動など
このように,1つの産業廃棄物処理事業に関しても,事業者の視点での位置づけと,地域住民・公共セクターの視点でのそれは,まったく異なる。しかし,産業廃棄物処理業者は,まったく異質の要求をもっているステイクホルダーに対して,等しく顧客と認識してその要求に応えなければならないのである。産業廃棄物処理業をはじめとする環境ビジネスの難しさとは,取引によって創出した効用の分配にあることが分かったが,それは各ステイクホルダー間で分配する効用の量と質の両方に関する困難さであることが理解できる。
(3) 廃棄物処理施設による価値の創出
環境施設の立地問題もまた,施設設置によって創出される価値の分配の複雑性で説明が可能である。廃棄物処理施設を設置し稼働することによる価値創出の構造を図 15に示した。都市ごみ焼却施設を例に解釈すれば,事業主体は自治体,受益者は自治体の住民である。事業によって効用(価値)が創出されると同時に,地元不利益すなわち負の効用(不効用)が創出される。地元不利益でない,正の効用を享受するのは,自治体と住民である。負の効用である地元不利益は,施設の地元住民が引き受けなければならない(受苦)。つまり,①自治体と②自治体住民そして,③施設の地元住民の3者(ステイクホルダー)が創出した効用(負の効用を含む)をそれら3者で分配するという,上に論じた産業廃棄物処理サービスの問題点と同様の構造をとるのである。
図 15 廃棄物処理施設の価値創出の構造
ここで,地元が負担する不効用を調整するために,通常は主に事業主体が地域コミュニティと交渉をしながら種々の操作を行う。まず,環境影響の緩和のために,環境影響の元となる事業の規模を調整することがある。埋立処分場の規模を縮小したり,焼却炉の運転時間を短縮したりの措置である。次に,技術的対応である。排水処理を高度化するなり,排ガス処理を強化するなりして環境影響を低減する,あるいは封じ込めるのである。そして,補償である。都市ごみ焼却施設であれば,施設の近隣に公園や文化施設を整備するなどによって,環境施設によって損なわれた地域の価値を補償しようというものである。実際の廃棄物処理施設の設置過程では,これらの操作を組み合わせて,地域コミュニティの同意を得ている。これら操作は,廃棄物処理という行為の一部であり,それによって得られる効用(価値)は,主に施設の地元に分配されるのである。
環境施設の立地について,地元との合意形成が困難になることが多いが,これはステイクホルダーの意識に,廃棄物処理が3者による価値創出であり適切な価値分配が必要であるとの認識が欠けることによる。問題の解決には,廃棄物処理に投資をしている共同生産者と認識されることが少ない地元コミュニティを,積極的に効用の創出に関与させ生産者化することである。すべてのステイクホルダーを生産者化するということは,ステイクホルダー間での交渉を可能とし,またすべてのステイクホルダーに対して,各自が投入した資源に応じて価値の分配をうけるという原則を適用することになる。具体的には,環境施設の立地選定の初期段階から情報公開を進め,住民参加を積極的に促すということになるだろう。このことは,環境施設の立地ばかりでなく,廃棄物処理事業の運営にも応用できるはずである。やはり,情報公開を進め,住民や行政の関与を高める措置となるだろう。
実は,すべてのステイクホルダーを生産者とすることで,環境に関するコンフリクトを克服する試みを実践している例がすでにある。アメリカ合衆国の化学工業協会(Chemical Manufacturer’s Association: CMA,現在はAmerican Chemistry Council)は,1990年代初頭から,会員各社に対して地域連携を強化するために,地域助言会議(community advisory panels: CAPs)の設置を呼びかけている(注[12])。その結果,1996年までに,300以上の化学工場で地域助言会議が設置されている。CAPsには,地域の住民のほか,専門家や環境活動家までもが参画している例がある。CAPsは定期的に会合を持ち,環境に関する事項を話し合う。CAPsメンバーに対する調査からは,会社経営者側と住民側の双方が,CAPsは地域社会と会社の間の信頼性を高めると評価しているという結果が出ている。CAPsとは,会社が自ら進んでコミュニティに対して情報を開示し,コミュニティに対して会社の環境保全策への参画を要請するものである。つまり,CAPsとは,受苦という形で環境価値の創出に参加していたコミュニティに対して,会社の環境保全策の決定への参画や,価値分配の交渉に就くことを促すものと理解できる。このことにより,会社の経営の自由度は削がれ,見かけの経営効率は低下するかも知れないが,長期的な安定と経営効率は向上するだろう。CAPsの手法は,環境問題の解決のために有効であることは証明されている訳であり,わが国における廃棄物処理に係る諸問題の解決にも応用が可能なはずである。
環境問題,特に事業活動と市民の間でのコンフリクトについては,種々の要素が複雑に絡み合い,問題解決はもとより問題の構造解明も困難なことが多い。しかし,ここで用いた,すべてのステイクホルダーが共同して価値を創出しているというマーケティング視点は,問題の構造を整理するのに有効である。なかんずくS-Dロジックは,物財のもたらす効用(価値)さえもサービスとして纏めてしまうので,物財およびサービス財ならびにバッズ取引までを共通の手法で取り扱うことができる,特に環境問題と馴染みが良く汎用性の高いロジックなのである。
3 交変系概念の適用
(1) 財貨のライフサイクルにおける産業廃棄物の発生
物財は,その原材料となる天然資源の採取に始まり,様々な過程を経て,消費者のもとに届けられる。Aldersonら(1964)は,このような天然資源から中間品揃え形成と変換,移転を経て最終消費者の手元に届けるまでの一連の取引を系としてとらえ,これをtransvection(交変系)と概念づけている(注[13])。彼らの記述を要約すれば,交変系とは,「最終消費者が手にする製品について,原材料からそこに至るまでのすべてのプロセスを包含する概念」であり,それを記号で表せばTv=STSTS ········· TSとなる(ここで,Sは選別sort,Tは変換transformationとする)。Aldersonらの概念には,付加価値については包摂するが,価値を付加すると同時に発生する廃棄物については言及していない。しかし,transvection概念に廃棄物という要素を加えることは容易である。
産業廃棄物は交変系の構成要素である各取引の段階で発生する。その後,最終消費者が使用した財貨は,最終的には廃棄されるに至る。このように,廃棄物は天然資源の採取にはじまる財貨のライフサイクルの各段階で発生し,最終的にはその財貨そのものが廃棄物となる。廃棄物のうち,天然資源採取から家計消費の直前までの各段階で発生するものが産業廃棄物である。産業廃棄物は,近年「副産物」と言い換えられる傾向にある。家計消費以降で発生する廃棄物は,通常は一般廃棄物として扱われる。ただし,産業財の場合は,消費以降で発生する廃棄物も基本的には産業廃棄物である(図 16)。図からわかることは,交変系とは,価値を付加すると同時に,廃棄物を発生して行く過程であることである。部分的には,「価値を付加するということは,廃棄物を分離することである」といえるだろう。たとえば,鉱石から金属を取り出す操作や,丸太から材木を切り出す操作などである。
図 16 財貨のライフサイクルと廃棄物の発生
天然資源を外国で採取し,製品となったものを外国から輸入すれば見かけの産業廃棄物発生量は減る。しかしこの場合,廃棄物の大部分は外国で発生している。現在,日本の産業構造は変化し,工業製品についても原料を輸入していたものが,部品を輸入するというようになってきているという。このことが,産業廃棄物の排出量の減少の理由の1つとなっていると考えられるが,産業廃棄物の発生を外国(資源産出国)にシフトしているだけであると理解することができる。
(2) 交変系
従来生産工程と廃棄物処理工程は,川の流れに擬えて川上・川下と言われたり,血流に擬えて動脈・静脈と言わたりしてきた。しかし,廃棄物処理系は交変系の一部として生産系と並行して存在するものであって,交変系の後に接続するのではなく,河川の上流・下流にたとえることは不適当である。また,動脈と静脈のような互いに逆方向の流れではなく,廃棄物処理系の経済的機能は生産系のそれと同方向であり,財に価値を付加することである。ただし,生産系において価値を付加する対象は,プラスの価値を持った財であるのに対し,廃棄物処理系においてはマイナスの価値を有するモノ(廃棄物またはバッズ)に対して価値を付加し,その価値をゼロまで,若しくはそれ以上の値に向上させるのである。すなわち,廃棄物処理系と生産系は,それらが取扱いの対象とする財貨の経済的価値が廃棄物処理系についてはマイナス価値であることだけが相違であり,その他の要素については差がない。生産系と廃棄物処理系は,財貨のライフサイクルの全過程にわたって常に共存し,時間を区切ってそれぞれ単独に存在し得ないものとし,両者が相互に作用する系が交変系であると理解すべきであろう。
図 16からは,廃棄物が交変系のあらゆる場面で発生していることがわかるが,それら廃棄物は,発生した時点で発生した者の負担で処理しなければならず,実際にそうされている。つまり,廃棄物の発生を生産工程の前方や後方に付け替えすることは不可能であり,またその処理費を他の取引段階で得られた利益によって賄うことも不可能なのである。さらに,財貨の価値には,その生産の背後にある廃棄物処理費用が織り込まれている。また,この廃棄物を含めた交変系概念は,物財の取引だけでなくサービス財取引を含むあらゆる取引に適用されるものである。
以上,産業廃棄物処理は交変系を構成する要素であるということが分かったが,そのことから,改めて認識すべき産業廃棄物処理の重要な特性が浮かび上がってくる。第1は,生産は,産業廃棄物処理と分離することができないということである。産業廃棄物処理がなければ,財貨を生産することはできない。また,すべての財貨の価格には,産業廃棄物処理費用が含まれている。換言すれば,すべての財貨の価値には,産業廃棄物処理の価値が織り込まれているのである。第2は,産業廃棄物処理サービスは,市場取引によって調達することが最適とは限らないことである。交変系内では,生産要素を調達する場合,価格メカニズムにもとづいて市場から調達することが合理的であるものもあるが,ヨリ高度な製品をヨリ効率的に作ろうという場合には,組織取引によって調達される事例は多く見られる。産業廃棄物処理も交変系を構成する生産要素であるので,このことが当てはまるだろう。
Aldersonは,交変系をTv=STSTS ········· TSと示しているが,ここにD(廃棄: disposal)という変数を導入して,Tv=STDSTDS ········· TDSとすることが可能である。ただし,Aldersonのオリジナルの交変系概念においては,変換(transform)に暗黙的に廃棄物処理が含まれるものとも考えることができるが,それを明示することは,産業廃棄物の本質を理解する上で有意義である。
脚注
(注[1])廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2。
(注[2])Kotler, P., Marketing Management : 11th edition, international edition, Prentice Hall Edition, 2003, pp.406-440.
(注[4])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,3ページからマーケティングと流通の関係についての記述を引用する。
メーカーと流通業者との関係は,それを規定する社会システムとしての流通機構の中で,多かれ少なかれ,決まってくるものであって,各々の企業のマーケティング戦略もこうした流通機構のあり方に規定される。だとすれば,誰がチャネル・パワーを行使できるかは,流通機構のあり方にも影響される。マーケティングの誕生期に主としてメーカーがチャネル・パワーを行使し,現在では大手流通業者もそれを行使できるようになったのは,流通機構の変化によるところが大きい。このことは,マーケティングの展開と流通機構のあり方が密接に関係していることを物語っている。
(注[5])細田衛士『グッズとバッズの経済学—循環型社会の基本原理』,東洋経済新報社,1999年,5-10ページ。
(注[6])Bucklin, L. P., A theory of distribution channel structure, IBER Special Publications, 1966.,邦訳 田村正紀訳『バックリン流通経路構造論』, 千倉書房,1977年。
(注[7])廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2。
(注[8])廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項。
(注[10])大友純「マーケティング・コミュニケーションの戦略的課題とその本質-プロモーション戦略の求心的要因を求めて」『明大商学論叢』,83巻1号,2001年5月205-213ページ。
(注[11])Vargo, S. L. and R. F. Lusch, “Evolving to a New Domination Logic for Marketing” in Journal of Marketing, vol. 68, January 2004, pp. 1-17.
Vargo, S. L. and R. F. Lusch,, “Service-dominant logic: continuing evolution” in Journal of the Academy of Market Science, vol. 36, 2008, pp. 1-10.
S-Dロジックを説明するために、Vargo and Luschは2004年の論文において、次の8つの基本的前提 (Fundamental Premise) を提示した。FP1: 専門分野に特化した技能と知識は、交換の基本的単位である; FP2: 間接的交換は、交換の基本的単位を隠す; FP3: 物財は、サービス供給のための物流機構である; FP4: 知識は、競争優位のための基本的な源である; FP5: すべての経済は、サービス(原語では複数)経済である; FP6: 消費者は、つねに共同プロデューサーである; FP7: 企業は、価値提案のみを行える; FP8: サービス中心の視点は、顧客志向であり顧客関係的である。
彼らは、2006年の著作と2008年の論文でこれら8つの基本的前提に使われる用語を整理したうえで、さらに2つの基本的前提を加えた。改訂のうえ追加された基本的前提は、次のとおりである。FP1: サービス(原語では集合的にとらえて単数)は、交換の基本的なベースである; FP2: 間接的交換は、交換の基本的ベースを隠す; FP3: 変更なし; FP4: オペラント資源は、競争優位の基本的な源である; FP5: すべての経済はサービス(原語では単数)経済である; FP6: 顧客は、つねにサービスの共同クリエーターである; FP7: 企業は、価値をもたらすことはできず、価値提案のみができる; FP8: サービス中心の視点は、本質的に顧客志向的であり顧客関係的である; FP9: すべての社会的行為および経済的行為の主体は、資源を取り纏める者である; FP10: 価値は、つねに受益者が個別に現象を見て決める。
(注[12])Lynn, F. M. and G. Busenberg, “Chemical Industry’s Community Advisory Panels: What Has Been Their Imapct?”, Environmental Science & Technology, vol. 34, no. 10(2000), pp. 1881-1886.
(注[13])Alderson, W. and M. W. Martin, “Toward a Formal Theory of Transactions and Transvections” in Journal of Marketing Research, vol. 11 (May 1965), pp. 117- 127.

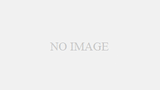
コメント