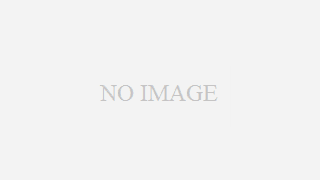 健康科学
健康科学 【離乳栄養法-6-③食物アレルギー】令和の時代~科学の進歩は赤ちゃんの食に関わる健康問題の解決に貢献しているか
令和時代~(2019~)食物アレルギーとは食物により免疫反応を介して生体に不利益(マイナス)な症状が引き起こされる現象をいう。不利益(マイナス)な症状は、食後2時間以内に起きて、30分~半日程度でおさまるのが一般的である。しかし重症になると...
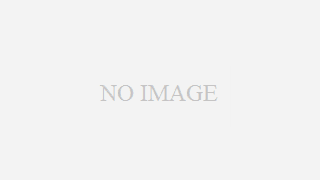 健康科学
健康科学 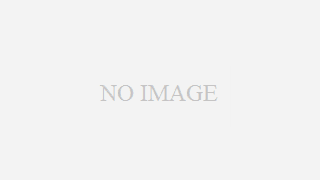 健康科学
健康科学 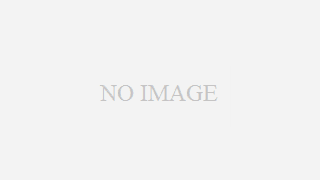 健康科学
健康科学 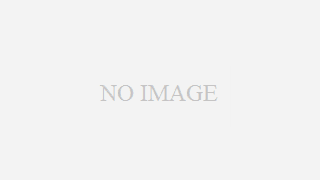 健康科学
健康科学 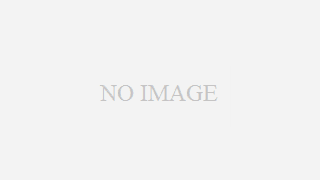 健康科学
健康科学 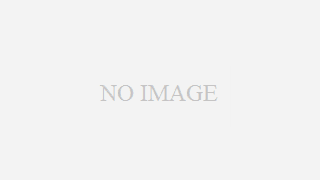 健康科学
健康科学 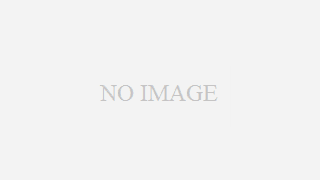 健康科学
健康科学 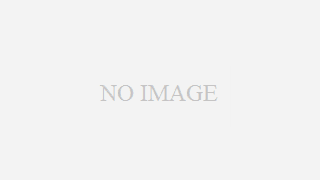 健康科学
健康科学 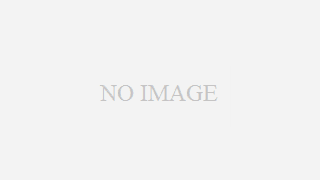 健康科学
健康科学 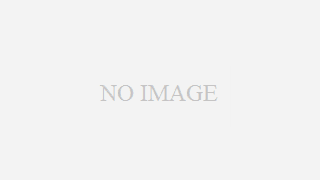 健康科学
健康科学