緒論
廃棄物とは
廃棄物とは,人間の活動に伴って発生するモノのうち,人間が不要とするモノである。人類が道具を持たず,定住社会を持たない時代にあっては,廃棄物にあたるものは人間自身の排泄物,或いは木の実の殻や動物の骨といった食物のかすに過ぎなかったであろうが,それらは生活環境に放置すれば人間の健康に害を及ぼすので,その時代であっても生活の系外に廃棄されていたことであろう。
その後,人類の生活は高度化するとともに高密度化し,廃棄物は計画的に管理しなければ,健康な人間活動が維持できなくなった。そこで,廃棄物を処理するという概念と行為が生まれた。初期には,廃棄物処理の主な要素は収集と投棄であり,投棄以降は自然の還元作用に任せるものだった。やがて,廃棄物の質と量が自然の容量を超えるようになると,焼却や管理された埋立など高度な技術を伴う処分を行うようになった。
このように,廃棄物は人間生活のあらゆる場面から発生し,また人類の歴史とともに存在するものである。そして,これまでの長い歴史のなかで,廃棄物処理の目的は一貫して,「公衆衛生の向上」と「生活環境の保全」であった。これが達成されなければ,人類は疫病に怯え,生活を維持することもできない。このことは現在も変わらない。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは,廃棄物のうちの事業活動から発生するものである。産業が高度化・大規模化する以前は,事業活動から発生する廃棄物であっても,人の生活から発生するごみと一緒に処理されることが常だった。その時代の事業由来の廃棄物は,量的にも質的にも生活由来のごみと区別が難しく,また事業由来の廃棄物と生活由来のごみを併せて処理することが経済的にも技術的にも最も合理的だったのである。
やがて,産業が高度化してくると,事業活動によって発生する廃棄物の中には,量的・質的に従来のごみ処理システムでは処理しきれないものが出てくるようになった。そこで,生活系のごみから「産業廃棄物」が分離されることとなった。わが国では,1970年に成立した廃棄物処理法で産業廃棄物が規定された。廃棄物処理法は,廃棄物を大きく2分し,事業活動にともなう廃棄物のうち,発生量が大きく公共の処理システムで処理が困難なものを「産業廃棄物」としてリストし,残るものを家庭からのごみを中心とする「一般廃棄物」とした。廃棄物処理法は,一般廃棄物の処理を市町村の責任とする一方,産業廃棄物の処理責任をそれを排出する事業者自身に負わせることとし,ここから事業者の委託を受けて産業廃棄物を処理する民間の産業廃棄物処理業者が生まれることとなり,今日に至る。
産業廃棄物は,廃棄物の一部である。このことから,産業廃棄物処理業の目的(使命)は,基本的には,上に述べた「公衆衛生の向上」と「生活環境の保全」である。ここに,事業活動に伴うという条件を付加すれば,「産業を支える」という第3の目的が加わることになる。産業廃棄物処理が円滑かつ安定的に遂行されなければ,自然環境・生活環境が破壊されることは容易に想像できる。しかし,産業活動にも影響することは気がつかないことが多い。産業廃棄物処理が止まれば,生産活動も止まり,人間の生活に必要な財貨の供給も止まる。それほど,産業廃棄物処理は重要であることを認識しておく必要がある。
産業廃棄物に関する問題点
産業廃棄物処理が生活者の目に触れることは希である。市井の人々の会話の中で,「ごみの始末に困る,ごみ出しが大変」などは良く聞かれるが,「産業廃棄物を見たことがある,産業廃棄物に触ったことがある」という話が聞かれることはないだろう。このように,生活者の目に触れないがゆえに,産業廃棄物に関してはある特定の一面だけが報道される傾向にある。すなわち,一般の人々に与えられる産業廃棄物関連の情報は,おもに不法投棄に関することに偏る。一方で,ごみの8倍もの量の産業廃棄物が処理されている様子を知る一般人は少なく,産業廃棄物の抱える真の問題を知る者も希である。ともあれ,産業廃棄物に関する問題の主なものは,次の通りである。
まず,産業廃棄物処理施設,とりわけ埋立処分場の設置が円滑に進まないことである。ある種の産業廃棄物処理施設は地域的に偏在して,産業廃棄物の量に比べて処理能力が過剰になることがあるが,埋立は慢性的な不足が言われている。埋立とは,廃棄物を収納するために空間を用意し,それを消費して行く行為である。稼働中の埋立処分場があっても,常に次の処分場の確保を進めなければならないが,種々の障害があってなかなか進まないのが現実である。
次に,民間の産業廃棄物処理業者の経営体力が弱いことが挙げられる。産業廃棄物処理の実行役である産業廃棄物処理業者のうち,株式を市場に上場している規模の者はわずかである。産業廃棄物処理の場合,業者が倒産すると,未処理の産業廃棄物在庫が残されることが多く,後始末に税金を使わざるを得ないケースもある。また,中小零細業者の参入と脱落が多く,そのことが業界構造を複雑にしているほか,行政による指導と取締の効率を悪くしていることが言われる。
そして,不法投棄である。不法投棄として摘発されるのは,年間およそ4億トン発生する産業廃棄物のうちのほんの一部であるが,その影響は大きい。不法投棄が産業廃棄物処理の信頼性・イメージを損ない,産業廃棄物に対する嫌悪感を生んでいる。そのことが,産業廃棄物処理施設の設置難などに繋がっている。また,暴力団の支配を受けた産業廃棄物処理業者が不適正な処理を大規模に行うなど,産業廃棄物処理業者の資質そのものが問題にされる事案が多い。
産業廃棄物は,普通の財貨,グッズ(goods)とは異なって,社会的・経済的に価値を有さず財としての性質を持たないバッズ(bads)である(注[1])。以上の産業廃棄物処理に関する問題点は,産業廃棄物処理がこのマイナス価値を有するバッズを扱うことに起因すると考えられている。本研究では,ここを中心に,産業廃棄物処理サービスの取引関係の成立過程を調べた。
海外の状況
ここまで日本の産業廃棄物処理について概観したが,簡単に海外の事情と比較する。ただし,廃棄物の定義および産業廃棄物の定義は,各国でまちまちであり,一概に比較することはできない。先進国においては,産業廃棄物処理を含む環境対策は,1972年の経済協力開発機構(OECD)の勧告「汚染者負担原則」に従っている。汚染者負担原則 (PPP: Polluter Pays Principle) とは,廃棄物処理ほか大気汚染防止や水質汚濁防止に対して,税金の投入を禁じる原則である。それら環境対策は,汚染者自身に負担させることにより,資源の配分を最適化し,また国際競争上の不公平をなくそうというものである。この原則は,環境汚染防止策と,公害補償に関する部分で一部に混乱もあるが,ここでは詳しく論じない。
わが国が産業廃棄物を法律で規定したのは1970年であるが,諸外国と比較して決して遅い方ではない。アメリカ合衆国が連邦法として産業廃棄物処理を規定したのは,1976年の資源保全回収法 (RCRA: Resource Conservation and Recovery Act) である。この法律は,主に有害廃棄物の管理を規定している。その後1978年には,廃用運河跡地に埋めた有害産業廃棄物が地下水位上昇によって地表に染み出たためにダイオキシンに汚染され,そのため一帯を強制疎開・閉鎖した「ラブキャナル事件(Love Canal incident)」が起きた。こうしたことを経て,国土全体が深刻な汚染状態にあることが明らかになり,1980年には通称スーパーファンド法,包括的環境対策補償責任法 (CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) が制定された。CERCLAにおいては,責任追及すべき汚染原因者の範囲を規定したほか,石油税などから基金(スーパーファンド)を設けて環境修復事業に取り組むこととなった。環境修復事業は,現在も進行中である。
欧州はEU統合以来,EUレベルでの廃棄物関係法令の整備が進められている。それら廃棄物関係法令は,資源回収や持続可能エネルギー源としての廃棄物への期待が高い。EUは,後から加入した旧東欧圏の諸国が,以前は西欧で発生した廃棄物の処分場所となっていた経緯がある。現在は,新規加入国の経済格差の是正とならび,環境レベルの整合も大きな課題となっている。
アジア各国は,経済成長が著しく,廃棄物とくに産業廃棄物の処理が問題になりつつある段階である。特に最近話題となっているのが,電子・電気製品の廃棄物である。いわゆるe-wasteからは,希少金属が回収できるが,環境規制が厳しい地域で回収するよりも規制が緩い地域の方が回収しやすい。そこで,回収をやりやすい地域で不十分な環境対策のまま希少金属の回収が行われている。アジア諸国のうち,e-wasteに対処した規制が制定され,それが十分に機能しているのは,わが国のほかに韓国と台湾だけであると言われている。また,アジア地域には日本企業が工場を移転する例が多いが,そうした工場が現地で環境問題を起こし,日本企業に責任が追及される例も出てきている(注[2])。
以上各地の産業廃棄物処理の状況を簡単に眺めた。環境対策は,各国まちまちである。その国の持っているリソースはそれぞれ異なり,そこで求められる環境保全レベルも異なる。それゆえ,環境規制が異なるのは当然である。しかし,廃棄物は国境を越えて移動できるし,水や空気といった環境媒体は地球全体で繋がっており,各国で異なる廃棄物規制のままで問題にならない筈がない。1976年に,「セベソ事件」が起きた。イタリア・セベソ市の農薬工場で爆発事故があり,ダイオキシンが飛散して一帯の土壌汚染を引き起こした。そこから除去された高濃度汚染土壌は,しばらくイタリアで保管されていたが,フランスに持ち込まれ,それがフランス政府からイタリアに引取要求され,その要求をイタリアが拒否するなどの複雑な経緯を経た事件である。これを契機に廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約が制定されて1992年から発効している。この条約に,わが国は1993年に加盟した。2011年現在の条約への加盟組織は,175カ国と1国際機関(欧州連合)である。台湾(中華民国)は,バーゼル条約に加盟していないが,廃棄物の輸出入をバーゼル条約に準拠した体制で管理している。バーゼル条約では,廃棄物の越境移動は厳しく規制される。これを受けて,日本の法律でも,廃棄物の国内処理原則が規定されるようになった。1999年の,わが国から回収資源として輸出されたものの中に医療廃棄物が混入していたために,フィリピンから2,300トンもの廃棄物をバーゼル条約に基づいて日本政府が引き取った事件は記憶に新しいところである。
震災の影響
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は,関連死を含めた死者行方不明者数は2万を超え,全半壊建物数は38万戸以上,住宅や工場などのインフラ被害額は17兆円に迫る未曾有の大規模な被害をもたらした(注[3])。特に,巨大な津波が,想定以上の広い地域を襲い,また万全の津波対策と考えられていた防潮堤なども機能しなかったことが人的被害を大きなものにし,改めてその恐ろしさを思い知るところとなった。この地震の前にも全世界的に多発する地震が多くの被害をもたらし,われわれは地震の恐怖を募らせていた矢先のことだった。2004年スマトラ島沖地震,2008年四川大地震,2010年ハイチ地震,2011年ニュージーランド地震などは,記憶に新しいところであり,人間生活に甚大な被害をもたらしうる規模の地震の発生が,確率的に決して小さくはないことを示すものである。
現在,特に課題となっているのは,がれき類をはじめとする震災廃棄物の処理と,原子力発電所に関する事項である。がれき類,すなわち建物の破壊によって生じた廃棄物の除去は,復旧・復興の基礎となる作業である。現在は,ゼネコンを主軸にして事業が進められている。環境省が2011年4月5日に発表した調査結果によると,宮城県・岩手県・福島県での建物破壊などによる災害廃棄物は,少なく見積もって2,490万トンで阪神・淡路大震災の約1.7倍以上に相当する。これは地域の通常のごみ処理量の16年分に相当する(注[4])。このような大量のがれき類の処理を迅速に進めるためには,日本全国の廃棄物処理能力を動員する必要であることは,1995年の阪神淡路大震災で既に経験していることである。今回の震災では放射能に関する混乱が影響して,広域処理をめぐる激しいコンフリクトが生じている。環境分野でNIMBY (Not In My Backyard)あるいは,LULU (Locally Unpleasant (Unwanted) Land Uses)と表現されるこのような状況が,震災に伴う放射能パニックによって,全国で引き起こされている。また,原子力発電所の今後の稼働に関しては,再開推進派・反対派ともに根拠あるデータを提示することもなく,感情的な主張を繰り返すばかりであり,協議による合意形成を目指す姿勢が見られない。
震災廃棄物(がれき類)の処理および原発をめぐるコンフリクトは,環境問題の中の特に興味深いケースである。すなわち,これらのコンフリクトは,生活環境・自然環境をめぐる攻防である。また,わが国の環境保全関連の制度や政策は,問題解決型である公害対策として始まり,環境保全すなわち予防型へと変化してきたが,今般のコンフリクトは近年まれになった公害対策型の課題である。そして,今まで経験がなく知識の及ばないものを受け容れることに対する人間の心理的側面を強く印象づけるものである。
本研究の目的
世界の状況を概観したが,本研究ではわが国の産業廃棄物問題に焦点を絞り込むこととする。わが国の産業廃棄物処理の特徴は,まず比較的早くから規制が整備されてきたことである。次に,狭い国土に高度な産業が集積しており,そこから発生する産業廃棄物であることである。わが国の産業は生産技術が高く材料の歩留まりが高いため,製品出荷量あたりの産業廃棄物の発生原単位は小さいと考えられるが,その反面ハイテク産業の製品ライフサイクルは短い。そのような条件下で,産業廃棄物は民間のサービス取引として処理されている。
産業廃棄物は,マイナスの価値を持つバッズとして経済学・社会科学の分析に供されてきた。バッズ経済は,普通のグッズ取引のように良い財を提供しても評価されないと言われてきた。つまり,産業廃棄物処理サービスの買い手である事業者にとっての物理的効用は,溜まった産業廃棄物が目の前から消えることだけであり,産業財取引の通念を延長して,産業廃棄物処理サービス購入時の比較の対象は価格だけであると考えられてきた。また,事業者は,価格には関心を持つものの,サービスのパフォーマンスには無関心なため,産業廃棄物処理業者に関する情報を積極的に探索しないことと,産業廃棄物処理業者が積極的な情報提供をして来なかったために,産業廃棄物処理に関する情報が不足する状況が続いて来た,そのことが良い産業廃棄物処理業者の成長を妨げてきたという指摘がなされている。
しかし,これらの通念をそのまま受容することはできない。産業廃棄物処理取引は複雑であり,それを一括りに論じることには無理がある。特に,買い手である事業者と,売り手である産業廃棄物処理業者の取引過程や,関係構築過程に関する組織的かつ実証的な調査・分析は,これまで実施されてこなかった。廃棄物問題については,これまで衛生工学,環境科学といった自然科学的視点からの研究と,それらにやや遅れて経済学の視点からの研究がなされてきた。経済学はマクロ的な視点によるものであるが,マクロ経済の基礎的な構成単位であるところの個々の企業や個人の取引といったミクロ経済の研究は多くはない。産業廃棄物処理の問題点を検証する上で,また先行きが見えづらい状況において産業廃棄物処理業者の生き残り策を検討する上で,産業廃棄物処理取引に関する実証的な研究が必要である。
そこで,個々の人間の購買行動や,経営態度といったミクロ的な事柄の実態をマーケティング的視点で調査し,その結果をもとに,事業者が産業廃棄物処理業者を選択し取引関係を構築する過程を明らかにすることを目的に本研究を進めることとした。
本研究の方法
事業者が産業廃棄物処理業者を選択する際に何を評価するのか,何が選定の決め手になっているのか,事業者の会社内の購買決定メカニズムはどうなっているのか,などを知るために,電子アンケートを実施した。アンケート対象は,法人組織とせず,勤め先で産業廃棄物処理に関与している個人とした。
これと並行して,産業廃棄物処理業者を対象とする電子アンケートを行った。事業者を対象とするアンケートと同様に,法人組織ではなく産業廃棄物処理業に勤務する個人を対象とした。アンケートでは,自社に対する自己評価と,同業者のうちで優秀だと思われる業者の評価を尋ねた。そして,この産業廃棄物処理業者を対象とするアンケートの結果と,事業者を対象とするそれの結果を突き合わせて解析を行い,その上で,解析結果を既往の知見と合わせて分析・解釈を行った。
本稿の構成
本稿は,産業廃棄物処理をその全体像の把握から始め,実証的調査を経て,ブランドの考察まで導くために,6章からなる構成とした。
第1章は,「産業廃棄物処理業の成立の経緯と現状」とし,わが国で産業廃棄物処理が法律で規定される以前のことを含めて,産業廃棄物処理業が成立してから今日までの経緯を概観するとともに,主に公式統計を用いて産業廃棄物およびその処理の現状を見た。並んで,産業廃棄物処理というビジネスについてその構造等について状況を整理した。
第2章は,「産業廃棄物処理の構造と機能」である。マイナスの価値を有する物財である廃棄物を処理することについて,物流面や価値の移転の面から検討を加えた。併せて,産業廃棄物処理業をはじめとする環境問題全体について,その構造と問題点について考察した。
第3章は,「産業廃棄物処理業の問題点」である。この章では,不法投棄の状況を主として公式統計を用いて把握し,バッズ経済としての産業廃棄物処理の特性と合わせて考察した。産業廃棄物に係る問題の多くは法規制の矛盾にあることを明らかにした。
第4章は,「産廃ブランド調査」である。ここでは,電子アンケートを行い,そこから得た結果と,その分析によって明らかになった事業者の産業廃棄物処理業者選択行動について記述した。また,優秀な産業廃棄物処理業者として票が集中した者について,業界内でのポジショニングを試みた。
第5章は,「産業廃棄物処理業における企業ブランドの展開」である。明らかになった高価値ブランドを形成しつつある産業廃棄物処理業者の例をもとに,産業廃棄物処理業におけるブランド形成の意味と,産業廃棄物ブランドの今後の展望について考察した。
第6章は,総括的な考察とした。
脚注
(注1)細田衛士『グッズとバッズの経済学――循環型社会の基本原理』,東洋経済新報社,1999年,5-10ページ。
(注2)わが国からアジア地域に進出した企業が引き起こした環境問題の典型例として,1983年に発覚したエイシアン・レア・アース社の事件がある。三菱化成が35%出資した同社は,オーストラリア等から鉱石をマレーシアに持ち込み,希土類の抽出を行っていたが,放射性を含む廃棄物による周辺住民への健康被害が問題となった。同社は90年代にはマレーシアから撤退した。
(注3)地震から1年後の2012年3月の段階で明らかになっている被害状況は,死者1万5,854人,関連死1,407人,行方不明3,155人,負傷2万6,992人,避難34万3,935人,建物全半壊38万2,246戸となっている。避難生活で体調を崩すなどして死亡した「関連死」は,岩手県・宮城県・福島県・茨城県・埼玉県で1,407人にのぼった。1995年の阪神淡路大震災では,死者6,434人のうち921人が関連死だった(「再生への底力今こそ――復興の歩みなお遅く」『日本経済新聞朝刊』,2012年3月11日)。
(注4)阪神・淡路大震災では,約1,450万トンの震災廃棄物が発生し,その処理費用は3,400億円だった(「東日本大震災―災害廃棄物対策の主な動向」『いんだすと』,2011年5月号,30-35ページ)。

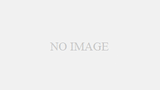
コメント