「おっぱいは誰のもの?」の連載目的は、現代において母が子に母乳を与えることを望みながらも、実現しにくい現状の問題解決の糸口を探ることであった。
先行研究では授乳という行為が生みの母の思いとは別に文化的要因に大きく作用されることが示されていた。このため今回は、文化的要因に関わる時代的背景を調べ、近世、近代、現代の時代的特徴と乳汁栄養法の関係について調べた。
江戸時代(近世)の、乳汁栄養法は人乳である。しかし現在のように母乳にこだわらなかった。人乳の種類は、母の乳、乳つけ、貰い乳、乳母の乳、であったが、その選択は身分差、貧富差、職業差、産褥期の母親の体調や生死の影響を受け、乳汁栄養法の決定権は家長にあった。この時代には、母親の乳が不足あるいは出産時死亡や産後の肥立ちの影響等で母親の乳を与えられない場合は、共村落共同体には、貰い乳というネットワークがあった。このネットワークにより農民や下層武士においては出産後間もない乳の出る女性から乳を貰い受けることができた。上層武士では知行地の百姓、雇い女、名主の嫁から乳を徴収した。身分の高い上層階級や富裕な町家では、母親に代わって乳を与える乳母を雇ったり、里子に出し乳母に育児を託したりした。生類憐み政策による捨て子取り締まり等で乳不足による捨て子の多かった江戸時代には乳汁確保の責任は重かった。しかしこれらを含む育児の責任は母親ではなく家長にあったのである。
明治時代から大正時代(近代)も、乳汁栄養法は人乳が中心であるが、人乳のなかでも、母乳が強調された。これは急速な近代化・産業化という国家の方針、家制度の再編、学制の導入により授乳を含めた子育ての責任が家長から母親へと転換した影響である。この時代から授乳を含め育児は母親の責任となりこれは現代まで続いている。ここに国家主導型子育て観の成立をみることが出来る。乳汁栄養法の選択も、母親の主体的な選択というより政策誘導型である。明治以降も富裕層では乳母を雇う習慣は続いていたが、一般には母乳栄養が主流であり、母乳が不足しているときには、乳母か、貰い乳による人乳でのサポートが行われた。
昭和前期も引き続き母乳栄養が主である。新生児には母乳を与えるのが原則で、不足しているときには貰い乳が勧められている。
戦時体制下には戦争のための人的資源増強を目的に、女性には丈夫な子どもを産み育てることが要求され、引き続き母乳が勧められている。不足の場合には牛乳やその加工品(練乳、粉乳など)が用いられていたが、戦争が長期化すると乳牛の飼育が困難になり、山羊乳を母乳の代用品とした。このような状況下において東京の京橋地区では母乳栄養は45%前後に減少した。しかし、長岡市では、80%を維持していた。一方、新生児体重は東京では変化が見られないが、大阪では70gも減少している。この状況から推察すると、乳汁栄養法ならびに栄養状態に地域差があったと考えられる。
戦後になると1953年までは母乳栄養は70%以上であったが以後50%近くまで減少し、改良の進んだ人工栄養の利用が増加した。しかし栄養法別乳児死亡率を見ると、人工栄養児の死亡率は1957年(昭和32年)の時点で母乳栄養:混合栄養:人工栄養=1:2:3とまだ高かった。
昭和後期から平成においては1970年代になるとさらに人工栄養が急速に増加し40%以上、母乳栄養30%と人工栄養の方が多くなった。
おもな理由として、
①人工栄養が進歩し乳児死亡率が母乳栄養と同率になった、
②核家族化により育児情報が伝承でなく近代医学を基盤としたものになり、さらにGHQの強力な指導の影響で医療機関での分娩が増加した、
③出産への医療の介入により妊産婦死亡率、新生児および乳児死亡率は減少したが、その頃の医療従事者は母乳育児支援への関心が低かった、
④母乳代替品のマーケティングの影響により安易に育児用粉乳を与える風潮が世界的に作られた、
等があげられる。
この状況に対して母乳栄養の確立が唱えられるようになり1974年よりWHO及び厚生省(現厚生労働省)を中心に母乳栄養推進運動開始された。その結果母乳栄養は50%近くまで回復したが、ダイオキシン騒動により、ふたたび母乳栄養が40%程度まで減少する。
平成からは、ダイオキシンなどの母乳汚染問題が落ち着き、母乳栄養が増え始めた。しかし新型コロナウィルス感染症の流行(2020年~2024年)の影響もあり2023年(令和3年)乳幼児身体発育調査(こども家庭庁)よれば、生後1~2か月34.5%、生後4~5か月39.2%と母乳栄養は少ない状況である。
こうして時代を追って乳汁栄養法の変動をみると、それぞれの時代的要因、特に政策の影響や感染症対策の影響を受けていることが明らかとなった。近代国家では人口政策や食料政策、感染症対策は欠かせないことであり、授乳への介入も当然といえるかもしれない。さらに近代化推進や戦争の影響を受けていることも頷ける。しかし高度経済成長以降の人工栄養の急激な増加と母乳栄養の低下は驚異的である。母乳は鉄、ビタミンKやDの含有量が低下しがちな一方、人工乳はこれらを適正に含んでいるという利点はある。しかし人工乳では初乳(母乳)で豊富なIgA抗体をはじめとする免疫グロブリン、補体、ラクトフェリン、リゾチームなどの免疫・感染防御物質を十分に補うことはできず、人工栄養児でも初乳の投与が望まれている。このような状況から厚生労働省が、母乳栄養の確立への支援を現在も続けているにもかかわらず、いまだに母乳栄養は40%程度と少ない。出産前には我が子を母乳で育てたいと望んでいた多くの母親の願いが叶わない現状を心から残念に思う。その願いが叶う世の中になるためには、母乳代替品のマーケティングの行き過ぎに注意すること、また母親が抱える授乳に関する困りごとに丁寧に対応できるようなシステムの構築が必要と確信する。
【おっぱいは誰のもの?ー乳児栄養法の変遷⑧】江戸時代~現代ーまとめー
 健康科学
健康科学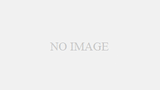
コメント